
2025年10月8日、化学の世界に大きなニュースが飛び込んだ。京都大学所属の北川進(きたがわ・すすむ)教授が、「金属−有機構造体(MOF:Metal-Organic Frameworks)」の発展という功績により、ノーベル化学賞を受賞した。
ただし彼の挑戦は、単なる材料開発にとどまらない。「物質に“空間”をつくる」──というその視点は、化学という学問の枠組みそのものを揺るがすものだった。
この記事では、彼の人生、研究の流れ、MOF のもたらす未来、そしてその社会的意義を丁寧に紡いで、読者に“北川像”を鮮やかに伝えたい。
経歴と背景:化学と出会い、深めた道
幼少期〜学び
1951年7月4日、京都市に生まれた北川進。幼少期から学問への強い探究心を持っていたという記録こそ多くは残っていないが、京都という土地ならではの文化的風土、そして日本の理論化学が育んできた環境が、彼の感性を育てたのではないかと想像される。
京都大学に進学し、理学部化学科で学び、博士号を取得。その後、教員・研究者として歩みを始める。
京都大学を拠点としながらも、国内外の研究機関との交流を重ね、研究ネットワークを広げていった。
所属・役割
ノーベル賞発表時点では、北川教授は京都大学の「研究推進担当 副学長(Executive Vice President for Research Promotion)」という役割も兼ねていた。大学全体の研究環境向上や支援体制構築など、運営面にも深く関わる立場だ。
また、京都大学の「物質−細胞統合システム拠点(iCeMS: Institute for Integrated Cell-Material Sciences)」にゆかりが深く、多孔性材料科学を含む学際研究の中心拠点の一端を担ってきた。
国際的にも評価が高く、英国王立協会(Royal Society)の外国会員 (ForMemRS) に選ばれているなど、その研究は世界に認められている。
研究の核心:MOF/PCP──“物質に空間を宿す”技術
MOF/PCPとは何か?
従来の化学物質観では、分子や固体は詰まっているもの、隙間なく結合しているもの、というイメージが強かった。だが北川教授らが注目したのは「空隙=孔(あな)」をいかに設計・制御するか、という視点だ。
**金属イオン(例えば亜鉛、鉄、銅など)**と、**有機配位子(有機分子が金属に結合する手を持つもの)**を組み合わせ、三次元的な格子構造を組み立てる。すると、格子の要素同士の間に「分子レベルの穴(孔)」が規則正しく現れる。このような構造体を、金属–有機構造体(MOF)または、配位高分子・配位ポリマー(PCP:Porous Coordination Polymer)などと呼ぶ。
この内部の孔は、サイズ、化学的性質、アクセス性(分子が中に出入りできるかどうか)などを設計して制御できる。これにより「物質の骨格でありながら、機能空間も兼ね備える」ハイブリッドな素材となる。
北川流の発展:安定性・可変性・応答性
MOF は1980〜90年代に萌芽的に研究されていたが、課題も多かった。特に、構造が壊れやすい、環境変化に弱いといった問題だ。
ここで北川教授が切り拓いたのは、次のような要素である:
- 構造安定性の工夫
金属・配位子の選択、結合強度、構造の補強設計などを通じて、外的刺激(温度変化、水環境、化学的侵食)に耐える MOF を生み出す技術。 - “軟質”・“可変性”を持たせる設計
固定的な格子構造だけでなく、外部刺激(温度変化、ガスの吸着、圧力、溶媒変化など)に応答して孔の大きさや構造が変化する MOF。「呼吸する結晶」「ソフト・ポーラス・クリスタル(Soft Porous Crystal)」という概念が、この流れを象徴する。
この可変性・柔軟性は、吸着・放出速度、選択性、再利用性といった実用性を飛躍的に高める。 - 機能化・応用付加
吸着・分離性能のみならず、触媒として機能を持たせたり、電気的性質・光応答性を導入したり、あるいは薬物運搬キャリアとして応用を考えるなど、MOF を“素材”としての枠を越え、システム材料へと押し上げた。
こうした諸要素が折り重なり、MOF は単なる「空孔を持つ材料」から、「空孔を操作し、応答させ、機能を発揮する材料」へと進化していった。
ノーベル賞授与理由と位置づけ
ノーベル化学賞の発表では、北川教授を含む三氏(北川進、Richard Robson、Omar M. Yaghi)が「金属−有機構造体(MOF)の開発」により受賞したとされている。
この功績には、単なる“新材料発見”というだけでなく、「化学構造設計の枠を拡張し、空間の観念を導入した点」に高い評価が与えられた。MOF は、未来の環境技術、エネルギー材料、ライフ科学応用など多方面へインパクトを与えうる“プラットフォーム技術”として位置づけられている。
MOF が拓く未来──応用と社会的意義
北川教授の研究は、化学界にとどまらず、環境技術、エネルギー、気候変動対策、医療、生体材料など広範な社会課題と重なっている。その可能性を、いくつかの将来像とともに探る。
気候変動・環境分野
- 二酸化炭素回収と貯蔵(Carbon Capture & Storage, CCS)
MOF は CO₂ を強く吸着し、選択的に分離する機構を持たせやすい。工場排ガスや空気中から CO₂ を除去し、さらに化学変換する素材基盤として注目されている。 - 水・空気浄化・有害物質除去
水中に存在する重金属イオン、有機汚染物質、化学物質(PFAS 等)を捕捉する機能を持たせる MOF の開発が進んでおり、水質改善や環境浄化への応用が期待されている。 - 乾燥地域での大気中水回収
乾燥した気候条件下で空気中の水蒸気を取り込み、液体水を取り出す技術。MOF は軽量で高効率な吸着材料として、水資源確保技術の一翼を担う可能性がある。
エネルギー・資源関連
- 水素貯蔵
クリーン燃料として注目される水素ガスを高密度かつ安全に貯蔵・輸送するには、ガスを吸着・放出できる材料が鍵となる。MOF はその候補として広く研究されている。 - 電池・触媒材料
電池正極や負極、電解質、または触媒支持体として MOF 構造を応用する研究も増えている。多孔構造を活かして反応性を高めたり、拡散を促進したりする設計が可能だ。 - レアメタル分離・回収
使用済み電池や電子廃棄物中のレアアース金属や希少金属を高選択的に抽出するための分離材料として MOF を設計する動きもある。
医療・生命科学
- 薬物運搬キャリア(ドラッグデリバリー)
分子レベルでの制御性と多孔性を活かし、薬剤を封入して標的部位へ運ぶキャリア材料として MOF が応用される可能性がある。更に、応答性(pH、温度、酸化還元など)を持たせて放出制御を行う設計も研究されている。 - センシング・診断
分子認識性を導入した MOF は、ガスや揮発性化合物を感知するセンサー材料、あるいはバイオマーカーを検出する診断材料としても期待されている。
受賞後の反響・語録・展望
国内・国際の反響
日本国内では、この受賞は大きな誇りと関心を呼んでいる。日本の化学界・科学政策コミュニティは、北川教授を「第9人目の日本人化学ノーベル受賞者」と報じている。
とりわけ、2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏以来、日本人化学者の受賞として期待されていた中での快挙でもある。
京都大学も、この偉業を機に(広報・研究体制強化・国際連携推進など)大学としての研究拠点整備や発信強化に力を入れるであろうとの見方が強い。
国際的にも、「MOF は21世紀の素材(materials of the 21st century)」と呼ばれる中、今回の受賞はその地位を確かなものとした。
北川教授の言葉・心構え
受賞発表後、北川教授は記者会見で次のように語っている。
「この賞は、私一人のものではありません。長年ともに研究してきた若い研究者、大学、支えてくれたすべての方々の努力と情熱の結晶です。」
また、今後についてはこうも語ったという。
「私は、“空間”の可能性を追い続けたい。空気中から材料を作る、空気を読み解く、物質の“余白”を使いこなす化学を追求したい。」
こうした言葉には、彼の研究者としての淡い情熱と同時に、化学を通して社会に貢献したいという強い覚悟が感じられる。
今後の課題と展望
受賞という名誉は一つの節目であって、ゴールではない。MOF を社会実装するためには、いくつもの壁が残されている。
- コストとスケールアップの課題
実験室レベルでは成功しても、産業規模で実用化するためにはコスト効率や量産の安定性が求められる。 - 耐久性・寿命
繰り返し使用に耐える性能、環境ストレスへの耐性、劣化抑制などが重要なテーマである。 - 安全性・毒性評価
材料自体やその分解生成物が人体・環境に安全であるか、長期的影響を考慮した評価が不可欠である。 - 統合システム化
MOF 単体で機能するだけではなく、センサー、電気系統、触媒、流体系との統合設計、制御技術と結びつけて“システム材料”として使えるようにする必要がある。
それでも、今回の受賞は、こうしたチャレンジが国際的にも期待されている証左である。北川教授らが開いた扉は、これから多くの研究者が行き来する“空間”の道である。
締めに:物質に「無」と「余白」を与えた化学者
北川進教授のノーベル賞受賞は、化学という学問ジャンルにおいて、極めて象徴的な意味を持つ。
「詰まっているもの」ではなく、「空隙を持ち、余白を活かすもの」へ。
物質そのものの定義を問い直し、そこに新たな可能性を見出した彼の業績は、21世紀科学の新しい地平を示すものである。
ときに科学は、「足し算」ではなく「引き算」で進む。
北川教授は、物質から“余白”を引き出すことで、新たな構造と機能を彫り出す彫刻家のようでもある。
未来はまだ見えない。しかし、「空隙を設計する科学」が、地球・人類にとっての希望の材料となる日が来るだろう。
そしてその核心にあるのが、“空間を制する化学”──それが、北川進教授が私たちに贈った知の贈り物である。

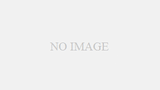
コメント