
世界が注目した「制御性T細胞」研究が人類の免疫観を変えた
■ 免疫の暴走を止める「見えざるブレーキ」
人間の体には、外敵から身を守るための精密な防衛システム――免疫がある。
だがその免疫が、誤って自分自身を攻撃してしまうことがある。これが「自己免疫疾患」だ。
リウマチ、1型糖尿病、潰瘍性大腸炎……。どれも免疫の暴走によって引き起こされる。
では、体は本来、どうやってこの暴走を防いでいるのか?
その謎を解き明かしたのが、2025年ノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人免疫学者、**坂口志文(さかぐち しもん)**である。
■ 坂口志文とは誰か
1951年、滋賀県長浜市に生まれた。
京都大学医学部を卒業後、免疫学研究の道へ。米国ジョンズ・ホプキンス大学やスタンフォード大学で研鑽を積み、帰国後は京都大学、理化学研究所などを経て、現在は大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授を務める。
坂口は若き頃から、免疫系の中に「抑制的に働く細胞が存在するのではないか」という直感を持っていた。
当時の免疫学は、「敵を攻撃する」側の仕組み――つまりアクセルを踏むメカニズム――を解明する研究が主流。
しかし坂口は、**「免疫にはブレーキがあるはずだ」**と信じて疑わなかった。
■ 世界を驚かせた1995年の論文
1995年、坂口の研究グループは歴史的な発見を発表する。
マウスの免疫細胞(CD4⁺T細胞)から「CD25⁺」という分子を持つ細胞を取り除くと、マウスは自己免疫疾患を発症。
しかし、このCD25⁺細胞を戻すと、病気が治まったのだ。
このCD25⁺T細胞こそ、のちに「制御性T細胞(Regulatory T cells, Tregs)」と呼ばれる細胞群である。
つまり、免疫の暴走を抑える「ブレーキ役」が実在していたのだ。
この発見は、免疫学の常識を根底から覆した。
それまで「免疫=攻撃」という一面的な理解だったものが、
「免疫=攻撃と抑制のバランス」という新たなパラダイムに進化した瞬間だった。
■ もう一つのピース、FOXP3遺伝子の発見
Tregsの存在が示されても、どうやってその細胞が生まれ、働いているのかは謎のままだった。
2001年、アメリカの研究者 Mary Brunkow と Fred Ramsdell(今回の共同受賞者)が、
Tregsの分化と機能を司るFOXP3遺伝子を同定。
坂口の研究チームは、FOXP3がTregsの「マスター遺伝子」として働くことを突き止め、
免疫のブレーキシステムの分子基盤を完成させた。
この連携研究によって、免疫寛容(自分を攻撃しない仕組み)の理解は分子レベルで確立された。
■ ノーベル賞選考委員会の評価
2025年10月、ストックホルム。
坂口志文、Brunkow、Ramsdellの3人にノーベル生理学・医学賞が授与された。
カロリンスカ研究所の発表文にはこうある:
「彼らの発見は、免疫系がいかにして自己を保護し、破壊的な自己免疫を防ぐかを解き明かした。
その洞察は、免疫の調和という新たな概念を人類にもたらした。」
坂口の受賞は、日本人として28人目、生理学・医学賞としては5人目。
湯川秀樹(物理学賞1949年)、本庶佑(医学賞2018年)と並び、
京都大学出身者として3人目のノーベル賞受賞者となった。
■ 「免疫を抑えること」が病を救う
坂口の研究がもたらした波紋は、基礎科学に留まらない。
Tregsの概念は、医学の多くの領域で応用されつつある。
- 自己免疫疾患:Tregsの働きを高めて免疫暴走を抑制する治療へ
- 移植医療:拒絶反応を抑える新しい免疫寛容療法
- がん免疫療法:逆にTregsを抑制することで、がんに対する免疫反応を強化
坂口は、大学発ベンチャー「RegCell(レグセル)」を設立し、
制御性T細胞を用いた新しい細胞治療の開発を進めている。
その目標は、「免疫のバランスを取り戻す医療」を実現することだ。
■ 「免疫とは戦いではなく、共生の科学」
坂口は受賞後の記者会見で、静かにこう語った。
「免疫とは、敵を倒すための仕組みではなく、
自分と他者の間に調和を築くための仕組みです。」
この言葉は、単なる科学者のコメントではない。
40年に及ぶ研究人生を通して、免疫の“陰の働き”に光を当て続けた男の哲学そのものだった。
■ 科学史の中での位置づけ
坂口の業績は、免疫学における第三の革命と呼ばれる。
1️⃣ 抗体の発見(20世紀初頭)
2️⃣ T細胞とB細胞の免疫機構の解明(1960〜80年代)
3️⃣ 制御性T細胞による免疫抑制の発見(坂口志文、1990年代)
免疫は、攻撃と防御、活性化と抑制というダイナミックな均衡の上に成り立つ。
坂口の発見は、その「均衡の科学」を生み出したと言っていい。
■ 研究者として、そして人として
坂口は研究室では温厚で、学生たちから「先生はいつも静かに考えておられる」と言われる。
派手な主張を嫌い、常に「データが語るべきだ」と言い続けてきた。
しかし、静かな語り口の奥には強い信念がある。
周囲がT細胞の「攻撃力」を競っていた時代、彼は一人で「抑える力」の研究を貫いた。
その信念が、30年の時を経て、ノーベル賞という形で世界に認められた。
■ 坂口志文の残したメッセージ
「免疫の目的は、敵を倒すことではなく、
体の中に“平和”を保つことなんです。」
その一言に、彼の研究のすべてが凝縮されている。
坂口志文は、免疫という複雑な宇宙の中に、
「戦い」と「寛容」、「秩序」と「自由」という哲学的な調和を見出した科学者である。
■ 未来への扉
T細胞の研究は、いま再び新しい段階に入りつつある。
人工的に制御性T細胞を増やし、移植医療や自己免疫疾患の治療に応用する臨床試験が進んでいる。
坂口の見据える未来は明快だ。
「免疫を敵ではなく、パートナーとして理解する時代」だ。
🧩 結びに
坂口志文のノーベル賞は、単なる科学の栄誉ではない。
それは、人間が自分自身の中にある“破壊と調和の力”を理解し始めたことの証でもある。
免疫という小さな宇宙の中で、彼が見つけたものは――
「生命のバランス」そのものだった。
🧠 坂口志文(さかぐち しもん)プロフィール
- 生年月日:1951年1月19日(滋賀県長浜市生まれ)
- 学歴:京都大学医学部卒、同大学博士(医学)
- 主な所属:京都大学再生医科学研究所 教授、大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教授
- 主な業績:制御性T細胞(Tregs)の発見と免疫寛容の分子機構の解明
- ノーベル生理学・医学賞(2025年)受賞
- ベンチャー企業RegCell創業者

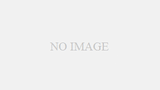
コメント